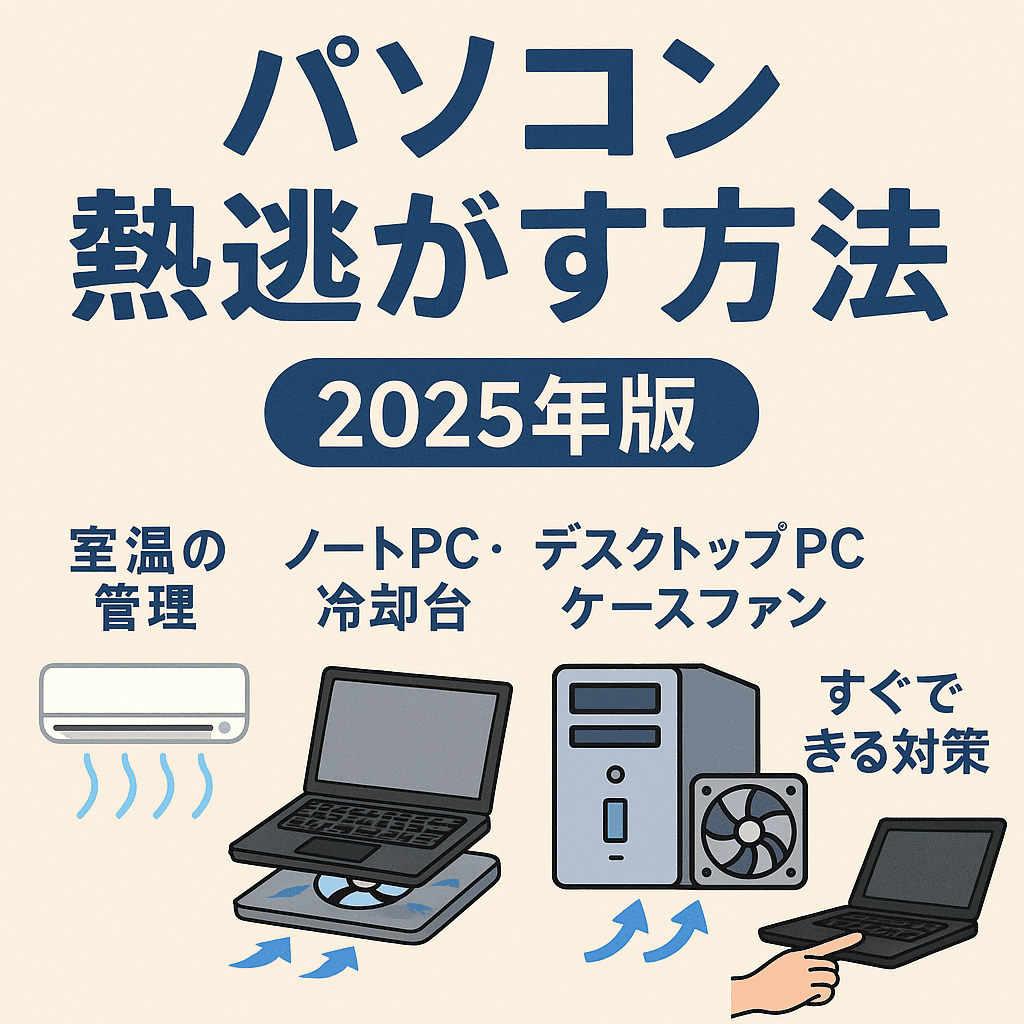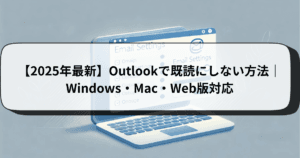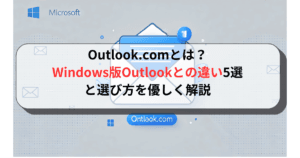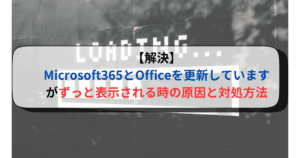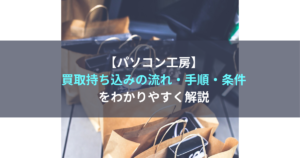パソコンを使っていると、ふと

「パソコン熱くなりすぎてない?」
と感じること、ありませんか?
長時間の使用や夏場の高温環境では、ノートPCもデスクトップも想像以上に熱をため込みやすく、
そのまま放置すると動作が重くなったり、最悪の場合は故障の原因
になることも…。
この記事では、「パソコン 熱逃がす」と検索した方に向けて、
実際に効果のある熱の逃がし方を、共通対策からデバイス別(ノートPC/デスクトップPC)対策
まで、具体的な方法で丁寧に紹介しています。
- 冷却台やファンの活用法
- 自作でできる放熱工夫
- さらには緊急時の正しい対処法
まで、今日からすぐ試せる内容が満載です。
「パソコンが熱い」と感じたら、早めの対策がカギ。
大切なPCを守り、快適な作業環境を取り戻すための一歩として、ぜひ最後まで読んでみてください。
1. 熱を逃がすために知っておくべき基礎知識
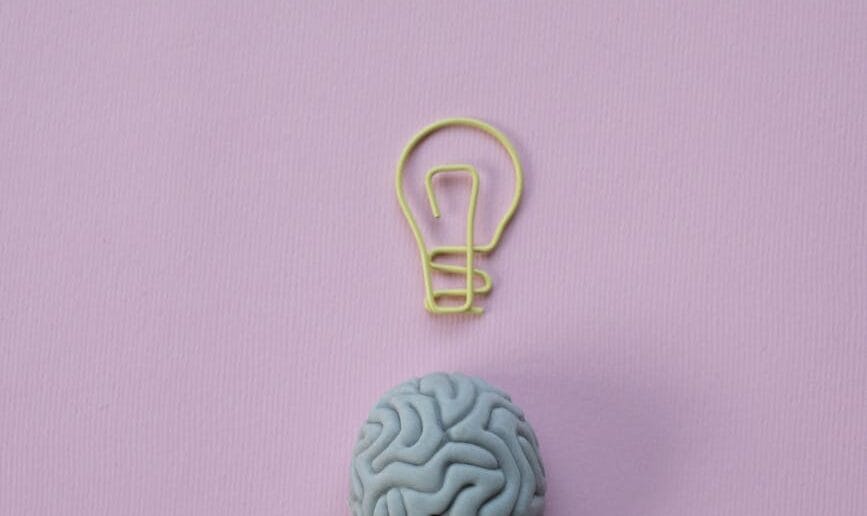
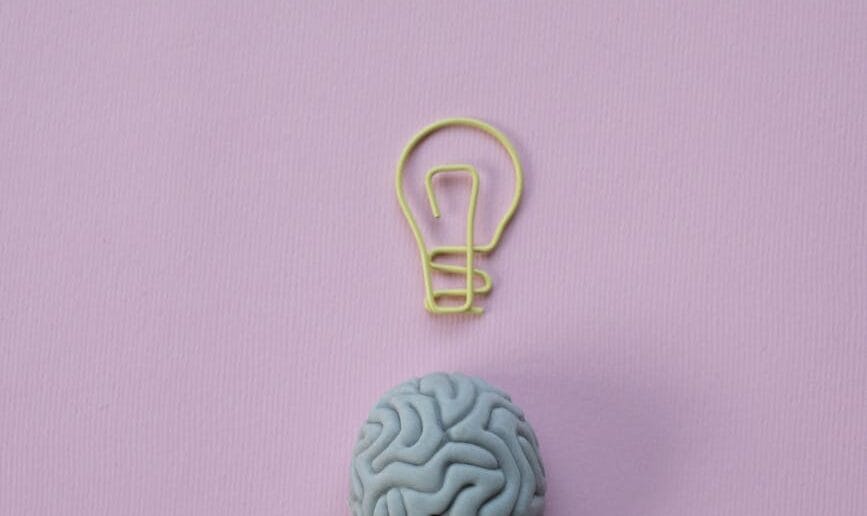
1‑1. なぜパソコンは熱くなるのか?CPU・GPU・熱暴走の仕組みを解説
まずパソコンが熱を持つのは、ごく自然なことです。
中でもCPUやGPUといった高性能な部品は、
処理を行うたびに大量の電力を消費し、その過程で熱を発生
させます。
たとえば
- 動画編集やゲーム
- Zoomのようなビデオ会議
をしているとき、パソコン内部はフル稼働状態になり、どんどん温度が上がっていきます。
このとき適切に熱を逃がせていれば問題ありませんが、熱がこもると「熱暴走」と呼ばれる現象が起きてしまいます。
熱暴走とは、パソコンが過熱により誤作動を起こしたり、自動的に性能を落としたりする安全機能です。
これはパーツの損傷を防ぐための仕組みですが、
逆にいうとそれだけ熱に弱い精密機械
であるとも言えます。



だからこそ、日常的に熱をうまく逃がしてあげることが、パソコンの寿命を守るためにも非常に大切なのです。
共通してできる“熱逃がす”基本対策(全機種共通)
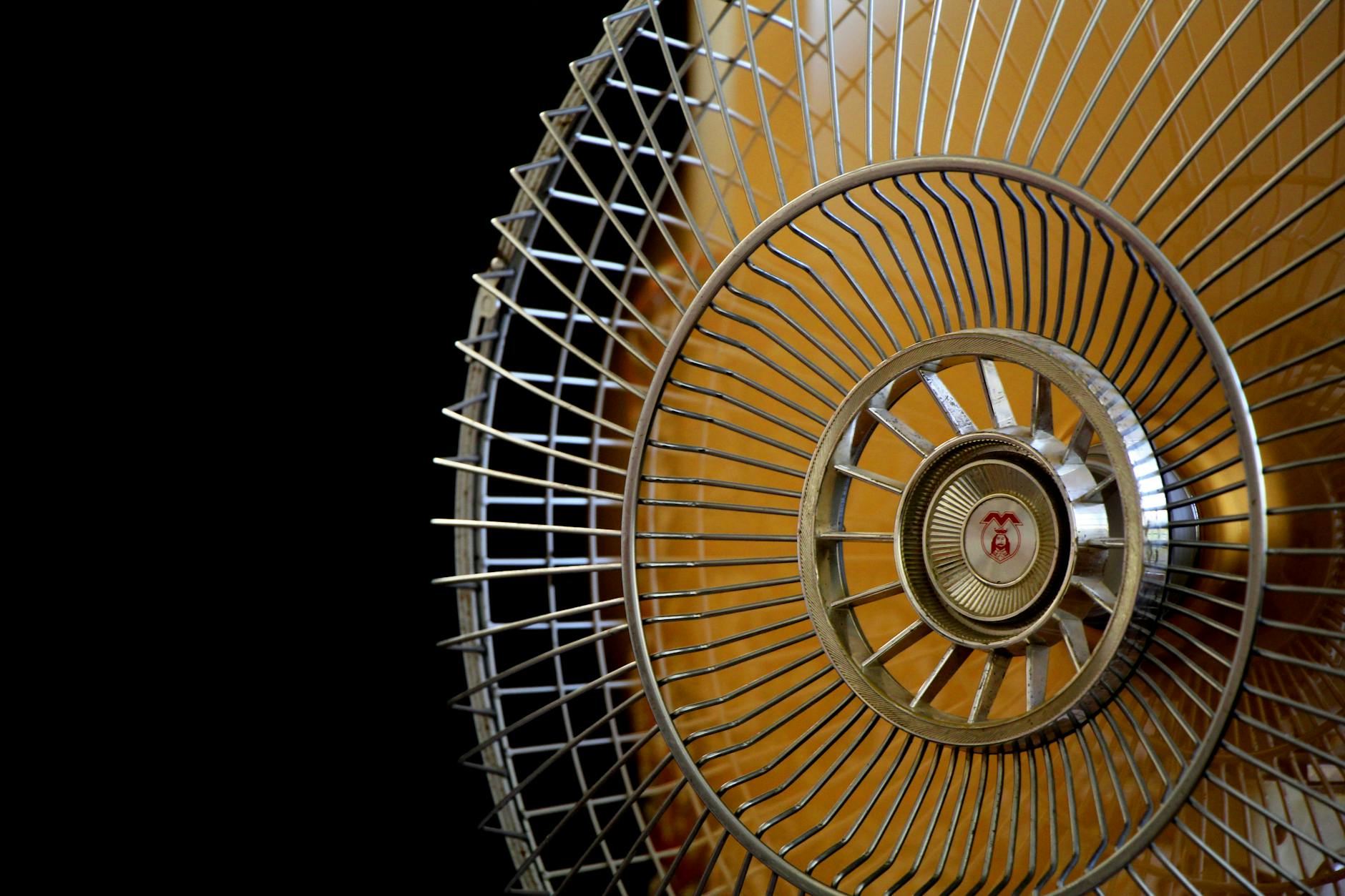
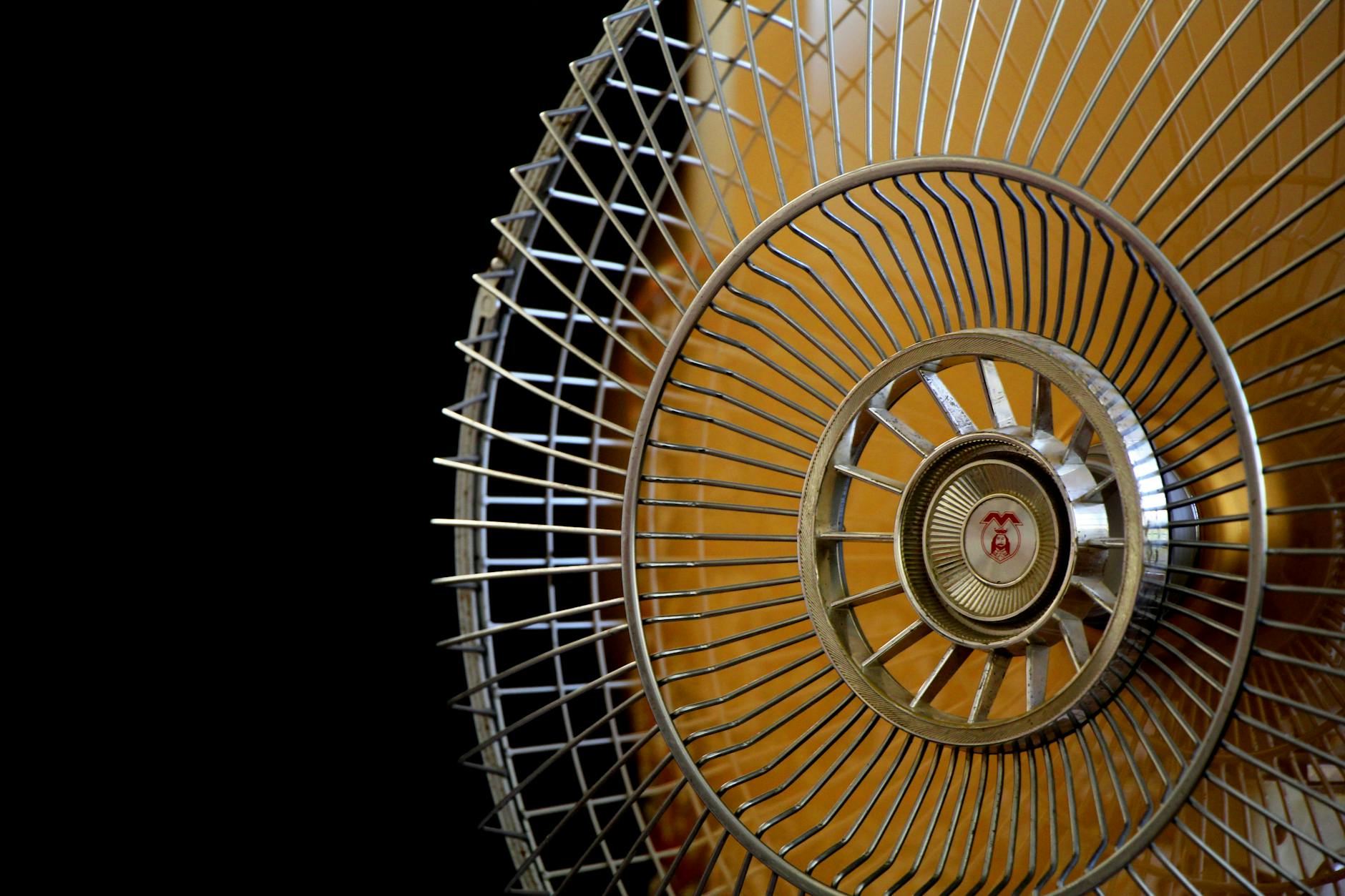
2‑1. 室温の管理:涼しい環境を保つコツと目安温度(例:25℃以下)
パソコンが発する熱は、外気温に大きく左右されます。
特に夏場の室温が
30℃を超えるような環境では、冷却ファンがいくら頑張っても排熱が間に合わず、本体がどんどん熱をため込んでしまいます。
理想の室温は25℃以下。
エアコンや扇風機を活用し、部屋全体を快適に保つことが第一歩です。



今なら、ミニの扇風機やUSBの扇風機もあるね
扇風機をパソコンの背面や側面に向けて風を当てるのも効果的。
なお、風を当てる場合は
吸気口・排気口の位置を確認し、風の流れを邪魔しないように設置
すると、さらに冷却効率がアップします。
吸気口・排気口の位置はパソコンの種類や機種によって異なりますが、基本的な目安は以下の通りです。
✅ ノートパソコンの場合
- 排気口(熱い空気が出てくる)
→ 背面や側面(ヒンジ近く)にあることが多い
→ 作動中に手を近づけると、温風が出ている場所が排気口です - 吸気口(空気を取り込む)
→ 多くの場合は底面(裏側)にある
→ 機種によってはキーボード面や側面に小さい吸気口があることも
📌 補足:
排気口が左右両側にあるモデル(ゲーミングノートなど)もあり、風を当てる際は排気を妨げないように注意が必要です。
吸気口に風を当てることで冷却効率は上がりますが、排気口には風を直接当てない方が良いです(熱がこもる恐れがあるため)。
✅ デスクトップPCの場合
- 排気口
→ 多くは背面上部にあり、ケースファンや電源ユニットから熱が排出される
→ 上部やサイドにあるタイプもあり、ケース構造による - 吸気口
→ 前面下部や底部にあることが多い
→ フィルターが取り付けられているモデルもある
📌 補足:
ファンの向きを見れば風の流れがわかります。
回転部分の裏側が「吸気」、前側(ブレードが見える側)が「排気」となります。
風を当てるときは、
吸気口に向けて風を送り、排気口から熱が自然に逃げるように
風の流れを意識すると効果的です。
意外と見落とされがちですが、室温管理は「最も簡単で効果の高い熱対策」です。
暑さを感じたら、パソコンも同じように熱がこもっている可能性があると考えて、まずは環境から見直してみましょう。
2‑2. 通気経路の確保:吸気・排気口を塞がないレイアウトと設置場所
パソコンの冷却は、空気の流れが命です。
吸気口から空気を取り入れ、内部の熱を排気口から外に逃がす構造
になっているため、この通気経路をふさぐと、一気に排熱効率が悪くなってしまいます。
よくあるミスが、
- 「柔らかい布製の上にノートパソコンを置く」
- 「デスクトップPCを壁にぴったりと寄せる」
といった使い方。
これでは吸気も排気も妨げられ、パソコンは熱の中に閉じ込められてしまいます。
理想的なのは、ノートPCであれば硬い平面(木製デスクなど)の上に置き、底面の通気を確保すること。
デスクトップPCであれば、壁から少なくとも10cm以上は空けて設置し、ケース内の風がスムーズに流れるよう配慮しましょう。
シンプルですが、「空気の通り道をつくる」だけでパソコンの冷却性能はぐんと高まります。
2‑3. ホコリ掃除の習慣化:エアダスター・分解クリーニングの頻度とポイント
パソコン内部のファンや通気口は、時間とともにホコリが溜まっていきます。
このホコリこそが、冷却性能を大きく下げる犯人のひとつ。
- 特にペットを飼っているご家庭
- 絨毯の部屋
などでは、驚くほど早くホコリが蓄積します。
ホコリを取り除く基本的な方法は、「エアダスター」での吹き出し。
パソコンの電源を切り、
排気口やキーボード周りにシュッと吹きかける
だけでも、かなりのホコリが取れます。
これを1ヶ月に1回程度行うだけで、ファンの回転効率がぐっと良くなります。
もっとしっかりメンテナンスしたい場合は、分解クリーニングもおすすめ。
ただし、自信がない場合はメーカー保証が効かなくなることもあるため、専門業者に依頼するのが安心です。
- 「パソコンがうるさいな」
- 「急に熱くなった気がするな」
と思ったら、まずはホコリ掃除を試してみましょう。
それだけで劇的に改善するケースも珍しくありません。
2‑4. ソフト・電源設定見直し:不要アプリ停止・省電力モード活用の具体手順
パソコンの発熱は、ソフトウェアの使い方でも大きく変わります。
- 裏で常に動いているアプリ
- 高負荷の設定のまま
使っていると、CPUやGPUが無駄に働いてしまい、それが熱の原因になります。
まず見直したいのが、スタートアップアプリ。
Windowsであれば、
- タスクマネージャー(Ctrl+Shift+Esc)を開く
- 「スタートアップ」タブ
から不要なアプリの起動をオフにできます。
次に省電力設定。
- Windowsでは「設定」
- →「システム」
- →「電源とバッテリー」
から、「バランス」または「省電力」モードを選ぶことで、CPUの無駄な負荷を抑えられます。
Macでは「省エネルギー」設定でディスプレイやハードディスクの動作を調整できます。
これらをこまめに見直すだけで、パソコンの発熱は確実に抑えられます。



設定一つで「静かになった」「熱くならない」と体感できることも多いので、騙されたと思って一度試してみてください。
ノートパソコンの熱を逃がす方法


3‑1. 冷却台タイプ(スタンド+ファン):メリット・デメリットと選び方
ノートパソコンを冷やす方法として定番なのが、冷却ファン付きの冷却台(クーラーパッド)です。
これはノートPCの下に敷いて、内蔵ファンで空気を送り、底面の排熱をサポートしてくれるアイテムです。



1年中使うことで、ノートパソコンを長く使えます。僕も使っています。
メリットは、設置がとにかく簡単なこと。
なかには、USBで接続するだけで風が送れるタイプもあり、デスク環境もスタイリッシュに整います。
一方で、風タイプはファン音が多少気になるという声や、持ち運びには少し不便といったデメリットもあります。
選ぶ際は、
- 風量(CFM)
- 静音性(dB)
- パソコンのサイズに合った台座の大きさを確認
するのがポイントです。
「PCが熱くて手が置けない」なんて場合は、この冷却台を一つ導入するだけで驚くほど快適になりますよ。
3‑3. 冷却パッド/シートタイプ:貼るだけの簡易対策の実用性と限界
「手軽に冷却したいけど、ファンの音が気になる」という方には、
冷却パッドやシートタイプ
も選択肢に入ります。
これは
熱伝導性の高い素材を使ったパッドを、パソコンの底面やヒートエリアに貼る
ことで、熱を外に逃がしやすくするというものです。
使い方は簡単で、ほとんどの商品が貼るだけのシンプル設計。
音が出ず、設置スペースも取らないため、静音性と省スペースを重視する方に向いています。
ただし、
効果はあくまで“補助的”なレベル
室温が高すぎる場合や、パソコンの内部温度が既に高いときには、これだけでは不十分なこともあります。



ぼくはパソコンではなくWi-Fiの中継器が熱くなりやすいので、そちらで使用しています
デスクトップパソコン


4‑1. ケース内部エアフロー最適化:ファン追加やケーブル整理など
デスクトップPCの場合、内部のエアフローを整えることが冷却性能に直結します。
エアフローとは、ケース内で空気がどのように流れているかを指します。
うまく風の流れを作らないと、せっかくのファンも十分な効果を発揮できません。
まず確認したいのが、吸気と排気のバランス。
前面から空気を取り込み、背面または上部からしっかり排出する流れが理想です。
必要であれば、ケースファンを1〜2個追加し、風量を強化しましょう。
もう一つの大事なポイントが「配線整理」。
ケーブルがごちゃごちゃしていると空気の流れが遮られ、熱がこもりやすくなります。
可能な限り裏配線を活用し、内部をすっきりと保つだけでも温度は変わります。
ケース内部のエアフローを意識すると、冷却性能はもちろん、見た目やメンテナンス性もぐっと良くなります。まさに一石三鳥の対策です。
注意点!
保冷剤・氷の使用はNG!結露による故障リスクを解説
「冷やしたいなら氷や保冷剤を使えばいいのでは?」と考えがち
ですが、これは絶対に避けたいNG行為です。
なぜなら、氷や保冷剤は外気との温度差により結露を引き起こし、パソコン内部に水滴が発生してしまうリスクがあるからです。
電子機器は水分に極端に弱く、わずかな水滴でもショートを起こしたり、サビの原因となったりします。
特に、ノートパソコンの裏に保冷剤を敷くなどの行為は、
すらあります。
一時的に冷たくなっても、結果的には寿命を縮めてしまうので、「保冷=安全」とは思わないことが大切です。
冷却は、風や自然放熱を使った“乾いた方法”で行うのが鉄則です。